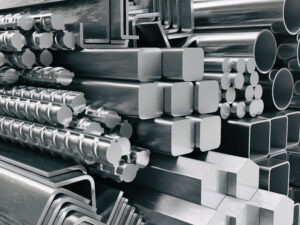POMプラスチックの色・種類と選び方を徹底解説:用途に応じた最適設計ガイド

POMプラスチックの色・種類と選び方を徹底解説:用途に応じた最適設計ガイド
POM(ポリアセタール)は耐摩耗性や剛性に優れ、歯車、軸受け、電子部品など幅広い分野で使用されるプラスチック素材です。ユーザーが最も知りたいのは「POMの色や種類によって特性はどう変わるのか」「用途に応じた選び方のポイント」です。本記事では、物性特性、色・種類の違い、選定時の注意点まで徹底解説します。
POMプラスチックの基本特性と種類
POMは熱可塑性樹脂で、強度と剛性に優れています。標準的なホワイト、ブラック、ナチュラルのほか、着色品や充填材入りの特殊グレードも存在します。色の違いによって紫外線耐性や耐摩耗性が若干変わる場合があるため、使用環境に応じて選定することが重要です。
詳しい種類の比較についてはPOMの種類と特性に関して解説で詳しく確認できます。(参考: JIS規格)
ホモポリマー系とコポリマー系の違い
ホモポリマー系は高剛性で摩耗耐性が高く、精密部品に適しています。一方、コポリマー系は吸水率が低く寸法安定性に優れ、湿度や水に晒される用途に向いています。具体的な用途と選び方はPOM選定ガイドに関して解説で詳しく紹介しています。
色による特性の違い
POMの標準色はナチュラルですが、ブラックやホワイト、着色グレードが利用可能です。ブラックは耐UV性に優れ、屋外用途に最適です。ホワイトやナチュラルは透明度や見た目を重視する用途で使用されます。着色品は色によって添加物が異なるため、耐摩耗性や耐薬品性に差が出ることがあります。
POMの加工性と用途別選定
POMは切削、旋盤加工、射出成形が可能で、加工性が良好な素材です。ただし、硬質で摩耗性が高いホモポリマー系は切削熱や工具摩耗に注意が必要です。歯車や軸受けなどの精密部品では寸法安定性と耐摩耗性を考慮して選定します。加工性の詳細についてはPOMの加工性と注意点に関して解説で確認できます。(参考: JIS規格)
用途別の選定例
- 歯車:ホモポリマー系ブラック、耐摩耗性重視
- 軸受け・スライド部品:コポリマー系、寸法安定性重視
- 電子部品ケース:ホワイト、耐熱性と外観重視
- 食品関連部品:FDA対応ナチュラル、無添加グレード
POMの長所と短所を理解した選び方
POMの長所は耐摩耗性、剛性、低摩擦係数、加工性の高さです。短所は吸水率や紫外線耐性の違いによる変形や色変化です。選定時には使用環境・荷重・温度・耐薬品性などを総合的に考慮することが重要です。
Pよくある質問
まとめ:色・種類・用途に応じた最適POM選定
POMプラスチックの色や種類は、用途や環境条件によって最適な選定が異なります。ホモポリマー系とコポリマー系の特性、色による耐UV性や摩耗性の違いを理解することで、失敗しない材料選定が可能です。用途別の選定ポイントや加工性の詳細は各リンク先で詳しく解説しています。