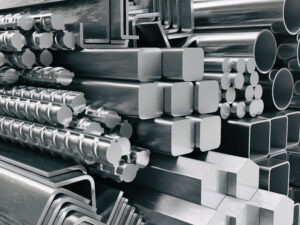チタンの強度を徹底解説|機械的性質から実用強度まで完全ガイド

チタンの強度を徹底解説|機械的性質から実用強度まで完全ガイド
チタンの強度とは|基本的な機械的性質
チタンの強度は、その優れた比強度(密度あたりの強度)によって航空宇宙、医療、化学プラントなど幅広い分野で評価されています。チタンの密度は約4.51g/cm³で、鉄(7.87g/cm³)の約60%、アルミニウム(2.70g/cm³)の約1.7倍です。この軽量性と高強度の組み合わせが、チタンの最大の特徴となっています。
チタンの強度を語る上で重要なのが、純チタンとチタン合金の区別です。純チタンは耐食性に優れますが強度は比較的控えめで、引張強さは270〜550MPa程度です。一方、チタン合金は添加元素によって強度が大幅に向上し、特にTi-6Al-4V合金は引張強さ900MPa以上を実現し、航空機部品や高性能スポーツ用品に使用されています。
チタンの機械的性質を評価する際には、引張強さ(材料が破断するまでに耐えられる最大応力)、降伏強度(永久変形が始まる応力)、伸び(破断までの伸び率)、硬度などの指標が用いられます。これらの値は材料の純度、熱処理条件、加工履歴によって変化するため、用途に応じた適切な材料選定が重要です。
また、チタンは温度依存性が比較的小さく、-200℃の極低温から約500℃の高温まで安定した強度を維持します。この特性により、極寒の宇宙空間から高温のジェットエンジン部品まで、幅広い温度環境で使用可能です。ただし、600℃を超えると酸素との反応が活発になり、強度低下や脆化が進行するため注意が必要です。
純チタンの強度特性
純チタンは工業用純チタンとして、JISでは1種から4種までグレード分けされています。数字が大きくなるほど酸素や鉄などの不純物含有量が多くなり、強度が向上する一方で延性は低下します。1種チタンは最も純度が高く、引張強さ270MPa以上、伸び27%以上という特性を持ち、優れた成形性と耐食性から化学プラントの配管や熱交換器に使用されます。
2種チタンは引張強さ340MPa以上、3種チタンは450MPa以上、4種チタンは550MPa以上と、グレードが上がるにつれて強度が向上します。実務では、2種チタンが最もバランスが良く、耐食性と強度の両立が求められる用途で広く採用されています。医療用インプラントや海水淡水化プラントの部材には、主に2種チタンが使用されています。
純チタンの降伏強度は引張強さの約60〜70%程度で、1種チタンで約170MPa、4種チタンで約480MPa程度です。この降伏強度は設計における重要な基準値となり、構造物が永久変形を起こさないための安全率計算に使用されます。純チタンは降伏後も比較的大きな伸びを示すため、過負荷時にも急激な破断を起こしにくいという安全性の高い特性を持ちます。
| 種類 | 引張強さ(MPa) | 降伏強度(MPa) | 伸び(%) | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| 1種(TP270C) | 270以上 | 165以上 | 27以上 | 化学装置、熱交換器 |
| 2種(TP340C) | 340以上 | 215以上 | 23以上 | 医療用具、海水淡水化装置 |
| 3種(TP450C) | 450以上 | 330以上 | 18以上 | 圧力容器、航空機部品 |
| 4種(TP550C) | 550以上 | 485以上 | 15以上 | 高強度構造材 |
チタン合金の高強度特性
チタン合金は、アルミニウム、バナジウム、モリブデン、スズなどの元素を添加することで、純チタンよりも大幅に強度を向上させた材料です。最も代表的な合金がTi-6Al-4V(64チタン)で、アルミニウム6%、バナジウム4%を含有し、引張強さ900〜950MPa、降伏強度830〜880MPaという高強度を実現しています。この強度は軟鋼(SS400)の約2倍に相当し、密度が約半分であることから、比強度では圧倒的な優位性を持ちます。
Ti-6Al-4Vはα+β型合金に分類され、室温でα相とβ相の二相組織を持ちます。この組織により、強度と靭性のバランスが良好で、溶接性や熱処理性にも優れています。航空機のエンジン部品、機体構造材、宇宙ロケットの燃料タンク、高性能自転車フレーム、ゴルフクラブヘッドなど、軽量かつ高強度が求められる用途で広く採用されています。
さらに高強度が必要な用途には、Ti-10V-2Fe-3AlやTi-15V-3Cr-3Al-3Snなどのβ型合金が使用されます。これらの合金は適切な熱処理(溶体化処理+時効処理)により、引張強さ1200MPa以上の超高強度を実現できます。ただし、加工性や溶接性はα+β型合金よりも劣るため、用途は限定的です。主に航空機の着陸装置部品や高応力がかかるファスナー類に使用されています。
チタン合金の強度は熱処理条件によって大きく変化します。焼きなまし状態(アニール材)では比較的低い強度ですが、溶体化処理後に時効処理を施すことで析出強化により強度が向上します。また、冷間加工による加工硬化も利用され、板材やワイヤーでは冷間圧延や冷間引抜きによって強度を高めることができます。実用部品では、これらの強化手法を組み合わせて要求強度を満たす設計が行われます。
| 合金種 | 引張強さ(MPa) | 降伏強度(MPa) | 密度(g/cm³) | 比強度(kN·m/kg) |
|---|---|---|---|---|
| Ti-6Al-4V(焼鈍) | 900〜950 | 830〜880 | 4.43 | 203〜214 |
| Ti-6Al-4V(溶体化+時効) | 1100〜1200 | 1030〜1100 | 4.43 | 248〜271 |
| Ti-10V-2Fe-3Al | 1200以上 | 1100以上 | 4.65 | 258以上 |
| Ti-3Al-2.5V(管材) | 620〜690 | 520〜550 | 4.48 | 138〜154 |
チタン強度と他金属の比較
チタンの強度を正しく評価するには、他の金属材料との比較が不可欠です。単純な引張強さだけでなく、密度を考慮した比強度(強度/密度)で比較することで、チタンの真の優位性が明確になります。航空宇宙産業や高性能スポーツ用品など、軽量化が重要な分野では、この比強度が材料選定の最重要指標となります。
鉄鋼材料との強度比較
鉄鋼材料は引張強さの範囲が非常に広く、軟鋼のSS400(400〜510MPa)から超高張力鋼(1500MPa以上)まで多様です。一般構造用鋼のSS400と純チタン2種(340MPa以上)を比較すると、引張強さはほぼ同等ですが、チタンの密度は鉄の約57%であるため、比強度ではチタンが1.75倍優れています。同じ強度を得るために必要な材料重量は、チタンの方が約40%軽量化できる計算になります。
機械構造用炭素鋼のS45C(引張強さ690MPa程度)と比較すると、焼鈍状態のTi-6Al-4V(900MPa)の方が引張強さで約30%高く、比強度では約2.3倍優れています。ただし、S45Cは焼入れ・焼戻しにより1000MPa以上の強度が得られるため、熱処理を考慮すると引張強さでは同等レベルになります。それでも比強度ではチタン合金が依然として優位です。
高張力鋼や工具鋼との比較では、絶対的な引張強さでは鉄鋼材料が優位となります。マルエージング鋼やばね鋼は2000MPa以上の引張強さを持ち、チタン合金の最高レベル(1200〜1400MPa)を大きく上回ります。しかし、これらの高強度鋼は密度が大きく、また耐食性に劣るため、防錆処理が必要です。総合的な性能評価では、用途に応じた適切な材料選定が求められます。
アルミニウム合金との強度比較
アルミニウム合金は密度2.7g/cm³程度で、チタン(4.5g/cm³)よりさらに軽量です。代表的な高強度アルミニウム合金である7075-T6は引張強さ570MPa程度で、純チタンとほぼ同等ですが、Ti-6Al-4Vと比較すると約40%低い強度です。比強度で比較すると、7075-T6が約211kN·m/kg、Ti-6Al-4V(焼鈍)が約208kN·m/kgとほぼ同等レベルになります。
ただし、アルミニウム合金は耐熱性に劣り、150℃を超えると強度が大きく低下します。一方、チタン合金は300〜400℃でも安定した強度を維持するため、高温環境ではチタンが圧倒的に優位です。また、アルミニウム合金は海水などの腐食環境に弱く、表面処理や定期的なメンテナンスが必要ですが、チタンは優れた耐食性により無処理でも長期使用が可能です。
コスト面では、アルミニウム合金がチタンの1/10〜1/20程度と大幅に安価です。そのため、常温環境で腐食の懸念が少ない用途では、アルミニウム合金が第一選択となります。航空機でも、客室内装材や低応力部品にはアルミニウム合金が使用され、エンジン周辺の高温部や高応力がかかる主要構造材にチタン合金が採用されるという使い分けがなされています。
ステンレス鋼との強度比較
ステンレス鋼は耐食性に優れた鉄系合金で、密度は約7.9g/cm³とチタンの約1.75倍です。代表的なSUS304(オーステナイト系)は引張強さ520MPa程度、SUS630(析出硬化系)は熱処理により1000MPa以上の強度が得られます。Ti-6Al-4Vと同等の強度を持つステンレス鋼と比較すると、チタンの比強度は約1.8倍優れています。
耐食性については、一般的な環境ではステンレス鋼も十分な性能を持ちますが、海水や高濃度塩化物環境ではチタンの方が優れています。特に、ステンレス鋼は孔食(局部的な腐食)や応力腐食割れのリスクがありますが、チタンはこれらの問題がほとんど発生しません。化学プラントや海洋構造物では、この耐食性の差が材料選定の重要な要因となります。
医療分野では、生体適合性の観点からチタンが優位です。人工関節や歯科インプラントには主に純チタンやTi-6Al-4V ELI(Extra Low Interstitial:超低不純物グレード)が使用されます。SUS316Lも医療用として使用されますが、長期埋植ではチタンの方がアレルギー反応のリスクが低く、骨との結合性(オッセオインテグレーション)にも優れています。
| 材料 | 引張強さ(MPa) | 密度(g/cm³) | 比強度(kN·m/kg) | 相対比強度 |
|---|---|---|---|---|
| 純チタン2種 | 340 | 4.51 | 75 | 1.0 |
| Ti-6Al-4V | 920 | 4.43 | 208 | 2.8 |
| SS400(軟鋼) | 450 | 7.85 | 57 | 0.76 |
| S45C(焼鈍) | 690 | 7.85 | 88 | 1.17 |
| SUS304 | 520 | 7.93 | 66 | 0.88 |
| Al 7075-T6 | 570 | 2.70 | 211 | 2.81 |
| Al 6061-T6 | 310 | 2.70 | 115 | 1.53 |
温度がチタンの強度に与える影響
チタンの強度特性を理解する上で、温度依存性は極めて重要な要素です。使用温度によって材料の強度、延性、靭性が変化するため、設計時には想定される温度範囲での機械的性質を考慮する必要があります。チタンは広い温度範囲で使用可能な材料ですが、それぞれの温度域で特有の挙動を示します。
低温環境での強度特性
チタンは低温脆性を示さない稀有な金属の一つです。鉄鋼材料の多くは低温になると延性が失われて脆くなる現象(低温脆性)を示しますが、チタンは-196℃(液体窒素温度)や-253℃(液体水素温度)の極低温でも延性を維持します。むしろ、低温では引張強さと降伏強度が上昇する傾向があり、Ti-6Al-4Vでは-196℃で室温の約1.2倍の強度を示します。
この特性により、チタンは極低温機器に理想的な材料となっています。液化天然ガス(LNG)タンク、液体水素貯蔵容器、宇宙ロケットの燃料タンク、超伝導磁石の構造材など、極低温環境で使用される機器にチタン合金が採用されています。特に宇宙開発分野では、軽量性と低温強度の両立が求められるため、チタン合金が不可欠な材料となっています。
ただし、低温環境では材料の熱収縮も考慮する必要があります。チタンの線膨張係数は約8.4×10⁻⁶/Kで、鉄鋼(約11.7×10⁻⁶/K)より小さいため、異種材料との接合部では熱応力の発生に注意が必要です。また、極低温からの昇温時には結露による水分の凍結・膨張も考慮し、適切な排水設計や断熱設計が求められます。
高温環境での強度変化
チタンの高温強度は、使用温度範囲によって評価が分かれます。純チタンは300℃程度まで、Ti-6Al-4Vは400℃程度までであれば、室温強度の80%以上を維持します。この温度域では、航空機エンジンのコンプレッサー部品や自動車の排気系部品などに使用されています。チタン合金は同じ温度域でのアルミニウム合金やマグネシウム合金と比較して、強度保持率が格段に優れています。
500〜600℃の温度域では、チタンの強度は室温の50〜70%程度に低下します。さらに、この温度域ではクリープ変形(一定応力下での時間依存的な変形)が顕著になるため、長時間使用する部品では許容応力を大幅に低減する必要があります。航空機エンジンのタービン前段部品など、高温高応力環境ではニッケル基超合金が使用され、チタン合金は比較的低温のコンプレッサー部に限定されます。
600℃を超える温度では、チタンは空気中の酸素と激しく反応し、表面に酸化層が形成されます。この酸化層は材料内部への酸素拡散を促進し、α-caseと呼ばれる硬化脆化層を形成します。この層は非常に硬いですが脆く、疲労強度を著しく低下させるため、高温での使用は避けるか、不活性ガス雰囲気での使用が必要です。真空中や不活性ガス中であれば、一部のチタン合金は800℃以上でも使用可能です。
熱処理と強度の関係
チタン合金の強度は熱処理によって制御できます。最も基本的な熱処理は焼鈍(アニール)で、加工歪みを除去して延性を回復させる処理です。α+β型合金では、β変態点(Ti-6Al-4Vでは約995℃)以下の温度で焼鈍を行い、通常700〜850℃で1〜2時間保持後、空冷または炉冷します。この処理により、加工硬化した材料は軟化し、延性が向上します。
溶体化処理+時効処理は、チタン合金の強度を最大化する熱処理です。まず、β変態点以上の温度(Ti-6Al-4Vでは950〜1050℃)に加熱してβ単相とした後、急冷(水冷または油冷)してマルテンサイト組織を得ます。次に、500〜600℃で時効処理を行うことで、微細なα相が析出し、強度が大幅に向上します。この処理により、引張強さを1100〜1200MPaまで高めることができます。
β型チタン合金では、さらに複雑な熱処理が可能で、時効温度や時間の制御により強度と靭性のバランスを調整できます。ただし、強度を高めすぎると延性や破壊靭性が低下するため、実用部品では要求される強度、延性、靭性のバランスを考慮した最適な熱処理条件が選定されます。航空機部品などでは、メーカー独自の熱処理規格が設定されています。
| 温度(℃) | 引張強さ(MPa) | 降伏強度(MPa) | 室温比(%) |
|---|---|---|---|
| -196 | 1150 | 1050 | 125 |
| -100 | 1050 | 950 | 114 |
| 20(室温) | 920 | 850 | 100 |
| 200 | 850 | 780 | 92 |
| 400 | 760 | 690 | 83 |
| 500 | 650 | 580 | 71 |
| 600 | 480 | 420 | 52 |
疲労強度と長期信頼性
実用環境では、静的な引張強度だけでなく疲労強度が重要な設計指標となります。疲労強度とは、繰り返し荷重を受ける部品が破壊に至るまでに耐えられる応力の大きさで、航空機、自動車、橋梁など、振動や変動荷重を受ける構造物の設計において必須の評価項目です。チタンの疲労特性は、材料の微細組織、表面状態、環境条件によって大きく影響を受けます。
チタンの疲労特性
チタンの疲労限度(無限回の繰り返しに耐えられる応力振幅)は、引張強さの約40〜50%程度です。Ti-6Al-4V焼鈍材では、疲労限度は約500〜550MPa程度となります。これは鉄鋼材料(引張強さの約50〜60%)と比較してやや低い傾向にあります。ただし、比強度で評価すると、チタン合金は鋼材と同等以上の疲労性能を持つと言えます。
チタンの疲労強度は表面状態に非常に敏感です。機械加工による工具痕、研削傷、腐食ピットなどの表面欠陥は応力集中源となり、疲労き裂の発生起点となります。そのため、高疲労強度が要求される部品では、表面を研磨仕上げにするか、ショットピーニング処理を施して表面に圧縮残留応力を付与することで疲労強度を向上させます。ショットピーニングにより、疲労限度を20〜30%向上させることが可能です。
切欠き効果もチタンの疲労強度に大きな影響を与えます。穴、溝、段差などの形状的不連続部では応力が集中し、疲労き裂が発生しやすくなります。チタンは切欠き感受性が比較的高いため、設計段階で応力集中係数を考慮し、フィレット半径を大きくとる、応力集中部を補強するなどの対策が重要です。有限要素法(FEM)解析を用いて応力分布を評価し、最適な形状設計を行うことが推奨されます。
環境の影響と腐食疲労
チタンは優れた耐食性を持ちますが、腐食疲労(腐食環境下での疲労)には注意が必要です。特に、海水環境や高温高圧水環境では、疲労強度が大気中よりも低下する場合があります。ただし、この低下率は鉄鋼材料やアルミニウム合金と比較すると小さく、チタンの耐食性の高さを示しています。海洋構造物や化学プラント機器では、この腐食疲労特性が材料選定の重要な要因となります。
水素脆化もチタンの長期信頼性に影響する要因です。チタンは水素を吸収しやすく、水素含有量が増加すると延性と疲労強度が低下します。特に、高温環境や陰極防食が施されている環境では、水素吸収が促進されるため注意が必要です。実用上は、水素含有量を管理値以下(通常0.015%以下)に維持することで、水素脆化のリスクを回避します。溶接時にも水素混入を防ぐため、適切なシールドガス管理が重要です。
航空機用途では、フレッティング疲労(接触面の微小振動による疲労)も考慮されます。ボルト接合部やリベット孔周辺では、僅かな相対変位による摩擦と繰り返し応力が複合的に作用し、疲労き裂が発生しやすくなります。対策として、適切な締付けトルク管理、干渉ばめの採用、表面処理による摩擦係数の制御などが行われます。
破壊靭性とき裂進展
破壊靭性は、材料中にき裂が存在する場合の破壊抵抗を示す指標です。チタン合金の破壊靭性(KIC)は、熱処理条件や組織によって変化しますが、Ti-6Al-4V焼鈍材で50〜80MPa√mです。高強度化した溶体化時効材では、強度は向上しますが破壊靭性は低下する傾向があり、30〜50MPa√m程度となります。実用部品では、強度と靭性のバランスを考慮した材料選定が重要です。
き裂進展速度は、既存のき裂が繰り返し荷重によってどの程度の速度で成長するかを示す指標で、損傷許容設計(Damage Tolerance Design)において重要です。チタン合金のき裂進展速度は、鋼材と比較して同等かやや遅い傾向にあります。これは、チタンの優れた延性により、き裂先端での塑性変形が大きく、エネルギーが吸収されるためです。航空機では、定期的な非破壊検査によりき裂を早期発見し、安全な運用を確保しています。
最新の航空機設計では、確率論的破壊力学を用いて、材料のばらつき、製造欠陥、使用環境の変動を考慮した信頼性評価が行われています。チタン合金の豊富な実績データに基づき、高い安全率を確保しつつ、軽量化を実現する設計が可能となっています。
チタン強度を活かす実用事例
チタンの優れた強度特性は、多様な産業分野で実用化されています。軽量高強度、耐食性、生体適合性といったチタンの複合的な特性を活かした応用例を、具体的な事例とともに紹介します。
航空宇宙分野での活用
航空機エンジンでは、チタン合金が多用されています。ジェットエンジンのファンブレード、コンプレッサーディスク、ケーシングなどに、主にTi-6Al-4Vが使用されています。回転する部品では遠心力が作用するため、軽量でありながら高強度を持つチタン合金が最適です。最新の大型旅客機エンジンでは、チタン使用量が1台あたり数トンに達し、エンジン総重量の約30〜40%を占めています。
機体構造では、主翼と胴体の結合部、降着装置(ランディングギア)、油圧システム配管などにチタン合金が採用されています。特に降着装置は、着陸時に機体の全重量を支える高応力部品であり、Ti-10V-2Fe-3Alなどの高強度β型合金が使用されます。この部品では、1200MPa以上の引張強さと高い疲労強度、優れた破壊靭性が要求されます。
宇宙開発分野では、ロケットの構造材や人工衛星の筐体にチタン合金が使用されています。宇宙空間では-150℃から+150℃以上の極端な温度変化があり、また打ち上げ時には強大な振動と加速度が作用します。チタンの広い温度範囲での安定した強度特性と、優れた疲労特性が、これらの過酷な環境に対応できる理由です。
医療分野での強度要求
人工関節は、チタンの強度と生体適合性を最大限に活かした応用例です。人工股関節のステム部分には、純チタンまたはTi-6Al-4V ELIが使用されます。人体の大腿骨に埋め込まれるこの部品は、体重の数倍の荷重を繰り返し受けるため、高い疲労強度が必要です。同時に、骨との結合性を高めるため、表面に多孔質構造を形成したり、ハイドロキシアパタイトをコーティングしたりする処理が施されます。
歯科インプラントでは、純チタン(主に4種)が使用されます。咀嚼時には数百ニュートンの荷重が繰り返し作用するため、十分な疲労強度が必要です。また、口腔内は唾液や食物による腐食環境であり、チタンの優れた耐食性が長期安定性を保証します。インプラント体は直径3〜5mm、長さ10〜15mm程度の小型部品ですが、20年以上の長期使用に耐える信頼性が求められます。
外科用器具にもチタン合金が採用されています。鉗子、剪刀、ピンセットなどの手術器具は、軽量で手に馴染みやすく、かつ十分な強度が必要です。Ti-6Al-4Vは、ステンレス鋼製器具と比較して約40%軽量でありながら、同等の強度を持つため、長時間の手術でも術者の疲労を軽減します。また、MRI検査時に磁性を示さないため、体内に残置する固定具にも適しています。
スポーツ・レジャー用品での応用
自転車フレームは、チタンの強度を活かした代表的なスポーツ用品です。競技用ロードバイクやマウンテンバイクでは、軽量性と剛性の両立が求められます。Ti-3Al-2.5Vやカスタムチタン合金を用いたフレームは、カーボンファイバーと比較して衝撃吸収性に優れ、長距離走行での快適性が高いと評価されています。溶接技術の進歩により、複雑な形状のフレームも製作可能となり、デザイン性と機能性を兼ね備えた製品が開発されています。
ゴルフクラブのドライバーヘッドには、Ti-6Al-4Vや独自開発のβ型チタン合金が使用されています。ヘッドの肉厚を薄くして大型化することで、スイートスポットを拡大し、飛距離と方向性を向上させています。フェース部分には1000MPa以上の引張強さを持つ高強度チタン合金を使用し、高速でボールを打ち出す際の変形を最小化しています。この技術により、初速を高めて飛距離を伸ばすことができます。
登山用品では、カラビナ、アイスアックス、テントポールなどにチタン合金が使用されます。登山では装備の軽量化が疲労軽減と安全性向上に直結するため、高比強度のチタンが理想的です。特に、カラビナは命綱となる重要部品であり、22kN以上の破断荷重が規格で要求されます。Ti-6Al-4V製カラビナは、同等強度のアルミニウム合金製と比較して約40%軽量化できます。
産業機器・化学プラントでの利用
化学プラントの反応容器、配管、熱交換器には、純チタンまたはチタン合金が使用されます。塩酸、硫酸、海水などの腐食環境下でも、チタンは優れた耐食性を発揮します。同時に、高圧条件下では十分な強度が必要であり、純チタン2種や3種が使用されます。特に、海水淡水化プラントでは、海水による腐食と高温高圧条件に耐えるため、チタン製熱交換器が標準的に採用されています。
発電プラントの復水器管には、純チタン管が広く使用されています。海水を冷却水として使用する火力発電所や原子力発電所では、従来の銅合金管が海水腐食により劣化する問題がありましたが、チタン管に置き換えることで、30年以上のメンテナンスフリー運用が可能となりました。薄肉化により重量あたりの伝熱性能も向上し、プラント効率の向上にも貢献しています。
| 用途分野 | 主要部品例 | 使用合金 | 要求強度レベル |
|---|---|---|---|
| 航空機エンジン | ファンブレード、ディスク | Ti-6Al-4V | 900〜1000MPa |
| 航空機機体 | 降着装置、結合部材 | Ti-10V-2Fe-3Al | 1200MPa以上 |
| 医療インプラント | 人工関節、歯科インプラント | 純チタン、Ti-6Al-4V ELI | 550〜900MPa |
| スポーツ用品 | ゴルフクラブ、自転車フレーム | Ti-6Al-4V、β合金 | 900〜1200MPa |
| 化学プラント | 反応容器、配管、熱交換器 | 純チタン2種、3種 | 340〜550MPa |
チタン強度を最大化する加工技術
チタンの強度特性を実用部品で最大限に引き出すには、適切な加工技術が不可欠です。チタンは「難削材」として知られ、加工には特有の技術とノウハウが必要です。ここでは、チタンの強度を損なわず、むしろ向上させる加工技術について解説します。
切削加工における強度管理
チタンの切削加工では、適切な工具選定と切削条件設定が重要です。チタンは熱伝導率が低いため、切削熱が工具刃先に集中しやすく、工具摩耗が早く進行します。超硬工具や多結晶ダイヤモンド(PCD)工具を使用し、切削速度を50〜100m/min程度(鉄鋼材料の1/3程度)に抑えることで、工具寿命を確保します。切削油を豊富に使用することで、切削熱を除去し、表面品質を向上させます。
加工後の表面粗さは疲労強度に直接影響します。粗い加工面は応力集中源となり、疲労き裂の発生起点となります。高疲労強度が要求される部品では、切削加工後に研磨仕上げを施し、表面粗さをRa 0.8μm以下(できればRa 0.4μm以下)に仕上げます。また、加工によって表面に導入される残留応力も考慮し、必要に応じて応力除去焼鈍を行います。
塑性加工による強化
鍛造加工は、チタンの強度を向上させる有効な手段です。熱間鍛造により、鋳造組織や粗大な結晶粒を微細化し、機械的性質を改善できます。Ti-6Al-4Vの鍛造材は、鋳造材と比較して引張強さが約20%向上し、特に疲労強度と破壊靭性が大幅に改善されます。航空機エンジンのディスクやブレード、重要な構造部材には、鍛造材が使用されます。
冷間加工による加工硬化も利用されます。板材の冷間圧延、管材の冷間引抜き、ワイヤーの冷間伸線加工により、転位密度が増加して強度が向上します。ただし、加工度が大きすぎると延性が低下し、加工割れのリスクが高まるため、適度な加工度(圧下率20〜40%程度)で強度と延性のバランスをとります。医療用ワイヤーやばね材では、この加工硬化を積極的に利用しています。
溶接と強度保持
チタンの溶接は、適切な条件下では母材と同等の強度を持つ接合が可能です。ただし、チタンは高温で酸素、窒素、水素と反応しやすいため、溶接中は完全な不活性ガスシールドが必要です。TIG溶接(タングステン不活性ガス溶接)では、表側シールドに加えて、裏側や溶接部周辺もアルゴンガスでシールドする必要があります。トレーリングシールドや裏波シールド治具を使用し、溶接金属の汚染を防ぎます。
溶接後の熱影響部(HAZ)では、熱サイクルにより組織が変化し、強度や靭性が変化します。Ti-6Al-4Vでは、HAZで若干の硬化が生じますが、適切な溶接条件であれば母材強度の90%以上を維持できます。重要構造物では、溶接後に応力除去焼鈍(500〜650℃、1〜2時間)を施すことで、残留応力を低減し、寸法安定性と疲労強度を向上させます。
表面処理による強化
ショットピーニングは、チタンの疲労強度を向上させる最も効果的な表面処理です。セラミックビーズやガラスビーズを高速で表面に衝突させることで、表面層に圧縮残留応力を導入し、疲労き裂の発生を抑制します。適切な条件でのショットピーニングにより、疲労限度を20〜30%向上させることができます。航空機部品では、標準的な強化処理として広く採用されています。
陽極酸化処理は、チタン表面に酸化被膜を形成する処理で、耐摩耗性と耐食性を向上させます。硫酸電解液中で陽極酸化することで、数μmの酸化チタン層が形成されます。この処理により表面硬度が向上し、摺動部品の耐久性が改善されます。ただし、酸化層は脆いため、過度の負荷がかかる部位では剥離のリスクがあります。
窒化処理は、チタン表面に窒素を拡散させて窒化物層を形成し、表面硬度を大幅に向上させる処理です。プラズマ窒化やガス窒化により、表面硬度をHV800〜1200まで高めることができます。切削工具やダイス、摺動部品など、高い表面硬度が要求される用途で有効です。ただし、処理温度や時間が不適切だと、母材の靭性低下や寸法変化が生じるため、慎重な条件設定が必要です。